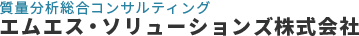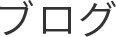逆相HPLCでリン酸塩緩衝液が多用されるのは?
カラムメーカーさんやHPLC装置メーカーさんの逆相HLCPのアプリケーションノートを見ると、リン酸塩緩衝液を用いた例が多いですよね。
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_application_data/L2129.pdf
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_application_data/L2027.pdf
http://www.kanto.co.jp/products/siyaku/pdf/s_mtyappli201203l.pdf
何故リン酸塩緩衝液がよく使われるのでしょうか?
昔から慣例的に使われていたという事は勿論あると思いますが、その主な理由は以下のような事です。
① 短波長領域(210 nm以下)に吸収をもたない。
② 酸性・中性・塩基性、3つのpH領域で緩衝能をもつため、移動相条件のpH検討が容易である。
210 nm以下の短波長にしか吸収をもたない分析種の場合、ギ酸や酢酸、TFAなどの有機酸をベースにした緩衝液は使えません。カルボニル基がその波長領域に吸収をもつからです。例えば、分析種として脂肪酸を分析する時などは、リン酸塩緩衝液を用いて200~210 nmの波長で分析できます。
緩衝液を検討する場合、緩衝能を示すpHは非常に重要です。3つのpH領域で緩衝能をもつリン酸塩緩衝液はとても使いやすい訳です。
この2つの特長をもつために、リン酸塩緩衝液は、古くからHPLCで分離条件を検討する際のファーストチョイスになっていたのだと思います。
私はHPLCを扱うようになったのは、LC/MSがキッカケだったので、自分自身では上記のような事は実体験にはないのですが。
一方、リン酸塩緩衝液のデメリットには以下があります。
① 酸性で長期間使用するとカラムの劣化が早い。
② 基本的にLC/MSに使えない。
世界中でLC-MS装置(インターフェース)が開発され始めた頃、私は既に日本電子に居て、同社オリジナルのLC-MSインターフェースであるFrit-FABの開発や応用を担当していました。その当時から、LC/MSにリン酸塩緩衝液を使いたいという要求はありました。そのために開発したのが、エムエス・ソリューションズのオリジナル技術である「ソルナックチューブ」です。
このブログでも以下に投稿していますが、「そもそもソルナックチューブとは?」と言うような基本的な内容はまだ投稿していませんでした。
https://www.sitsuryobunsekiya.com/blog/264808.html
https://www.sitsuryobunsekiya.com/blog/289411.html
このホームページは数年前に完全リニューアルしたのですが、その前のホームページには、ソルナックチューブの事は詳しく書いてありました。
次の機会に投稿したいと思います。